【初学者向け】電験3種の初期段階での勉強法は”急がば回れ”で臨むべし!
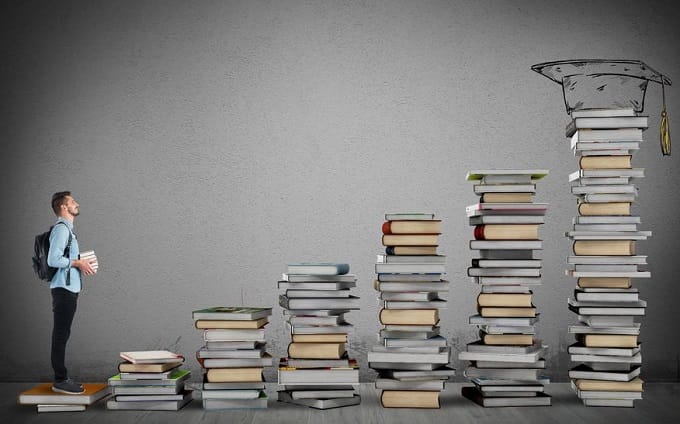
4月は何かとキリの良いタイミングなので、この時期から秋の電験3種の本試験に向けて勉強を開始される方も多いかと思いますが、そのタイミングに合わせてか、ここ最近、勉強法に関する質問をポツポツとメールで頂いております。
質問を頂く都度、電タクの体験/経験レベルでの回答をさせていただいておりますが、特に電験3種の初期段階での学習に関する質問が非常に多いです。
例えばこういった質問。
※質問者様には掲載の許可を得ております
現在、電験3種の勉強を進めていますが、理論が理解できずにいます。
恥ずかしながら直流回路の項目で問題を何回か解いてやっと理解できる状態です。
こんな状態でこの先の交流回路や磁気作用の項目も理解できるのかと思っています。
現在使っている参考書は、やさしく学ぶ電験三種というものですが、別の参考書で勉強した方が良いのでしょうか?
なにか良い勉強方法等ありましたらご回答お願いします。
電タク自身も電験3種を開始した当初は同じような気持ちになった憶えもありますので、おそらく多くの方が同じような悩みを抱いているんじゃないでしょうか?
そこで、本記事では「勉強開始でスタートダッシュ ⇒ 即デカイ壁出現」といった方向けに電験3種の初期段階での勉強法についてまとめてみたいと思いますので一緒に見ていきましょう!
最初から電験3種の参考書から始めると確実にヤラれます!
あくまでも個人的主観になりますが、ビジネス系などの資格試験の場合、「試験勉強を始めよう=資格対策の書籍で進める」という流れが一般的だと思いますが、電験3種においてはこの方程式が成り立たないように感じます。
というのも、電験3種の場合は電気数学や電気に関する物理学の知識などのある程度の下地となる知識/スキルが必要となります。
元々、高校や大学の電気科卒の方や低圧/高圧の電気関係の仕事をされてる方であれば、そういった下地の部分はある程度出来ていると思いますので、とっつきやすい科目から勉強を始める流れでよいですが、そうじゃない方(文系出身/仕事も完全に異業種 etc…)の場合だと「ナニコレ??」となってしまうことが避けられない状況になると思います。
また、試験の特性上、丸暗記すればなんとかなるモノではなく理解をしながら解法をカラダで覚えていくことが必要となるため、理解の壁に阻まれてしまうと著しくモチベーションが落ちるであったり、早い段階で挫折をしてしまうことになります。
なので、まずは自身の下地となる知識/スキルが電験3種の学習に耐えうるべき状態にあるかをしっかりと見極めていく必要があります。
下地の知識/スキルがなければまずはそこを仕上げていく
では、その下地となる知識/スキルがない場合、どのようにして仕上げていけばよいか?という話になってきますが、電タク自身が行っていた勉強法を例に解説していきます。
その1:
電気数学の参考書をひたすらやり込む
電タク自身、元々、理系出身ではありましたが、三角関数やベクトルの考え方など10年以上のブランクがあったため、完全に知識が抜け落ちておりましたので、まずは数学の知識/スキルを仕上げていくところに焦点を当てて取り組んでおりました。
勉強開始当初は、非常に手こずった記憶がありますが参考書を2回転するころにはある程度の下地が出来てきたという実感が湧いてきました。
なお、過去に数学そのものをまともに勉強したことがない方の場合、もう1段階前のところから始める必要がありますが、以前に以下の記事でその辺りをまとめておりましたので紹介しておきます。
ちなみに電タクは上記記事で紹介している「電気工事士のためのかんたん数学入門」という参考書を購入して勉強を行ってました。
 | 新品価格 |
こちらは第二種電気工事士の筆記試験に必要な数学の範囲に絞り込んであり、この手の本の中では比較的ボリュームも少ないためそれほど時間をかけずに学習することが出来ると思います。
その2:
電気理論に関する学習を行う
「その1」である程度の数学知識が身に付けば、電験3種の勉強を開始しても良いとは思いますが、この状態ではまだ少しハードルが高く感じると思います。
そこで、電タクの場合は少し遠回りとなりますが、電気工事士向けの数学本を買って勉強した流れで、第二種電気工事士の筆記試験用の参考書を購入し勉強を行っておりました。
正直なところ、電タク自身、直流回路/交流回路などの電気理論に関する勉強などをまともにしたことがなかったのもあり、いきなりその範囲のラスボス級と戦うことに不安を感じたということもありましたので、少し遠回りをする道を選んだってことになります。
言うなれば、来るべきボス戦に備えて武器を揃え、経験値をひたすら上げる作業といったところでしょうか。
で、電タクの場合、バカ正直に第二種電気工事士の試験範囲全てを対象に勉強をしておりましたが、今思い返せばそこまでする必要はなかったかと思います。
基礎理論にあたる範囲は電験3種の「理論」に色濃く継承されてますのでマストで勉強をしたほうがよいと思いますが、鑑別などのところに関しては電験3種の「電力」科目でソレっぽい内容と類似する部分もありますが、初期段階で覚える必要は全くないと言えますのでバッサリと切り捨てることをお薦めします。
※鑑別の範囲をやる時間があるなら基礎理論をもう一周するほうがコスパが断然イイですw
なお、実際に使っていた参考書をご紹介したかったのですが、かなり前に知人にあげてしまった&どの本だったか忘れてしまったため、とりあえず巷のオススメ本をご紹介しておきます。
 | ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士筆記試験すいーっと合格2017年版 新品価格 |
↑写真やイラストによる解説が豊富なので文字アレルギーの方におすすめ
 | 新品価格 |
↑上記の「すいーっと」よりは中級者向けのテキスト。技能範囲は不要なのですがテキストとしての全体評価は高めなのでご紹介
仕上がり具合を見極めたうえで電験3種のテキストに臨もう

上記の学習範囲を一通りこなせば、晴れて電験3種の学習を開始することが出来る状態となりますが、もし電気数学の範囲、電気理論の範囲で理解出来ないところがあるならば、個人的にはそこを完全に理解出来るレベルにまで持っていってからのほうがよいと考えております。
電験3種の学習内容は、おそらくそこで引っ掛かる数倍難易度が高い内容と感じますので、中途半端な状態で臨んでしまうと間違いなく返り討ちに遭うと思います。(なぜなら実際に電タクがそうだったから(爆 )
で、ここで言う「理解出来るレベル」についてですが、電タク的には問題の解答をみれば「あー、そうだった!」と思えるレベルかどうかだと考えております。
解答を見て分かるってことは解法自体の暗記はしていないが理解はしているという判断が出来ますので、まずはそのレベルまでイケてるのであればOKでしょう。
若干、理解という点において判断が甘いところがあるかもしれませんが、こちらの記事でご紹介している「電験3種遠回り勉強法(今名付けました)」に関しては「完璧に解ける」ことが目的ではなく、あくまでも理解の下地作りが目的だと考えてますので、あまり多くの時間をかけずに仕上げてもらえればよいかと思います。
まぁ、電験3種の初期段階での学習方法については、様々なアプローチ方法があるかと思いますが、こちらの記事でご紹介している勉強法が参考になるようであれば是非取り入れてもらえれば幸いです^^
■記事のまとめ
- 「電験3種の試験対策=電験3種の参考書から始める」は成り立たないことが多い
- まずは下地となる電気数学/物理の電気理論の知識・スキルを身につける
- 電気数学本→第二種電気工事士の筆記対策本の流れがおすすめ
- 「理解=気付けること」にフォーカスし下地を作っていく


[スポンサーリンク]
人気ブログランキングの応援よろしくお願いします!
ここまで読んで頂きありがとうございます。本日の記事は、いかがでしたか?あなたにとって少しでも参考になりましたら
クリックの応援よろしくお願いいたします<_ _>

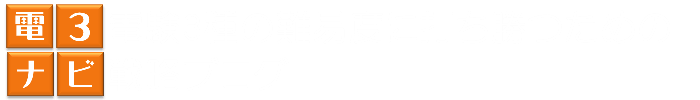
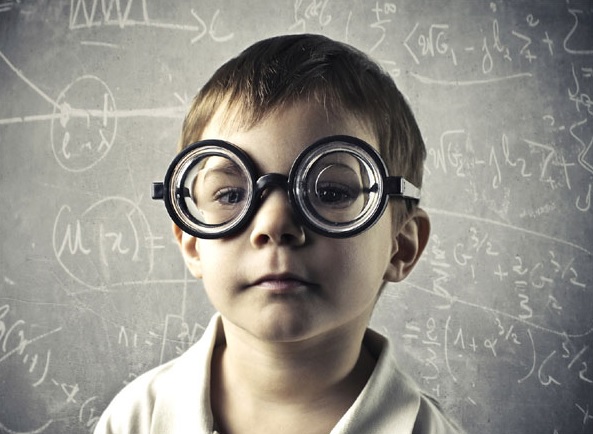

みんなのコメント